はじめに
「なんとなく体がだるい…」「いつもの薬が効かない」「自然な治し方をしたい」
そんなとき、ふと思い浮かぶ“漢方薬”。でも、種類が多すぎて何を選べばいいのかわからないという声も多く聞きます。
この記事では、市販で購入できる漢方薬を、症状ごと・目的ごとにわかりやすく紹介。登録販売者の視点から、選び方や注意点もやさしく解説します。
先に結論!漢方薬は「症状+体質」の掛け合わせで選ぶ
- 冷え・疲れ・むくみ → 当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)など
- 胃腸虚弱・慢性的な胃もたれ → 六君子湯(りっくんしとう)など
- イライラ・不眠・ストレス → 加味逍遙散(かみしょうようさん)など
- 生理不順・更年期の不調 → 桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)など
- 便秘がち・排便が硬い → 麻子仁丸(ましにんがん)など
“なんとなく”で選ばず、症状と体のタイプを見極めることが大切です!
症状別:代表的な漢方薬と特徴
| 症状 | 漢方薬 | 特徴・適した体質 | 商品例 |
|---|---|---|---|
| 冷え・むくみ・貧血気味 | 当帰芍薬散 | 冷えやすく、体力があまりない人向け | ツムラ漢方当帰芍薬散、クラシエ当帰芍薬散など |
| 胃腸の弱さ・食欲不振 | 六君子湯 | 虚弱体質で胃が弱い人におすすめ | ツムラ六君子湯、コタロー六君子湯など |
| イライラ・不安・不眠 | 加味逍遙散 | ストレスを感じやすく、神経が高ぶりやすい人 | ツムラ加味逍遙散、クラシエ加味逍遙散など |
| 更年期障害・生理トラブル | 桂枝茯苓丸 | 冷えとほてりが混在、血の巡りを整える | ツムラ桂枝茯苓丸、大正漢方桂枝茯苓丸など |
| 便秘・硬い便 | 麻子仁丸 | 便が硬くなりやすい人、腸の動きが鈍い人向け | ツムラ麻子仁丸など |
市販薬と漢方薬の違いとは?
市販薬(いわゆる一般的な西洋薬)は、特定の症状に対して「速やかに効く」ことを目的としています。一方、漢方薬は「体質やバランスを整える」ことで、じわじわと根本からの改善を目指します。
| 比較項目 | 市販薬(西洋薬) | 漢方薬 |
|---|---|---|
| 効き方 | 即効性が高い | 徐々に整える(体質改善) |
| 対象 | 症状そのもの | 症状+体質(冷え・虚弱など) |
| 成分 | 化学合成成分が中心 | 生薬(自然由来) |
| 服用期間 | 短期的に使用 | 継続して使用することで実感 |
どちらが優れているというより「目的に応じて使い分ける」ことが大切です。
Q1. 効き目が出るまでどれくらいかかる?
A. 漢方薬は“体質を整える”目的のため、即効性は少なめ。数日〜1週間程度の継続でじわじわと効果を実感するケースが多いです。
Q2. 食前・食後どちらで飲むの?
A. 基本的には「食前または食間」に服用するのが一般的。胃に内容物が少ない方が吸収が良くなるとされています。
Q3. 他の薬と併用しても大丈夫?
A. 成分が重複しない限り基本的に併用可能ですが、不安な場合は薬剤師や登録販売者に確認を。
登録販売者的アドバイス
- 正直な話、店頭で漢方薬について聞かれても、すぐに答えるのが難しいことは多いです。それだけ漢方は奥が深く、一人ひとりの体質や症状を丁寧に捉える必要があります。
- ですが、その分「自分に合ったものを選べたときの効果」はとても実感しやすく、相談のしがいがあるジャンルでもあります。
- 漢方薬は“効く薬”ではなく“整える薬”として理解すると選びやすくなります。
- 同じ症状でも「冷えタイプ」「のぼせタイプ」で使う処方が変わることがあります。
- 体質が合わないと効果が実感しにくいので、合わないと感じたら無理せず切り替えましょう。
まとめ
- 漢方薬は「症状」だけでなく「体質」も重要な選び方のポイント
- 即効性よりも“体質改善”を目指す薬。1〜2週間の継続で判断する
- 不安がある場合は、登録販売者や薬剤師に相談を!
自分の体と向き合う第一歩として、漢方薬を活用してみませんか?

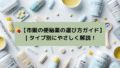

コメント